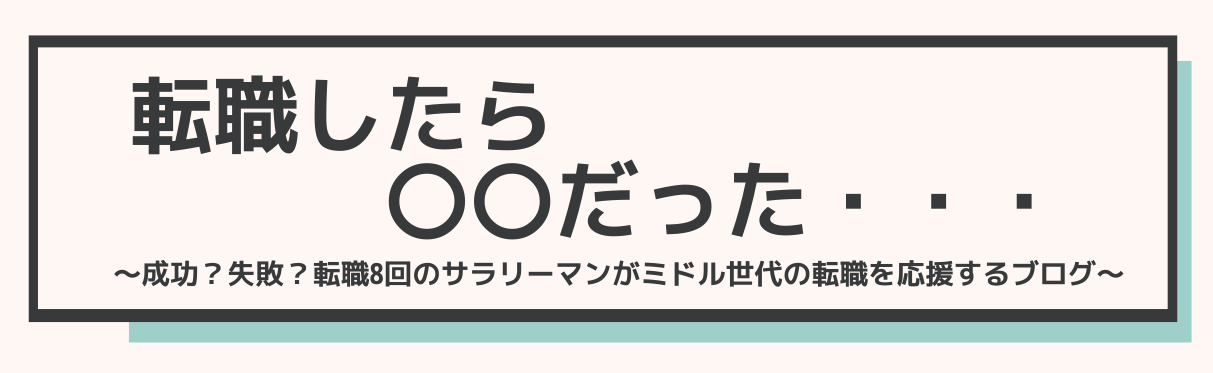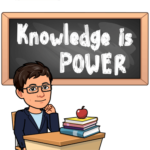「新卒で外資系はやめとけ」は本当?10回転職の筆者が解説!

「新卒で外資系に行くのはやめとけ」― 就活中に一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?
高収入・グローバルな環境に惹かれつつも、
すぐクビになるのでは?
英語が不安
研修がなくてついていけないかも
と不安に感じる人は多いはずです。
実際に外資系企業は成果主義で厳しい一面がありますが、それだけが真実ではありません。
筆者は、新卒で日系企業に就職し、日系企業間での転職経験を経て、40代半ばで外資系企業に転職しました。
個人的にはもう少し早く外資系に移れば良かったと思っています。
その中で感じたのは、「最初の選択=一生の方向性」ではないということです。
この記事では、日系と外資の違いを整理し、外資に向く人・向かない人の特徴、そしてキャリアを築くための現実的な選択肢 を具体的に紹介します。
外資が合う人には大きなリターンがあり、逆にまず日系で基礎を作ってから外資に挑戦する「ステップアップ戦略」も有効です。
- 新卒で外資が「やめとけ」と言われる5つの理由とその先回り対策
- 日系企業に新卒で入るメリット(育成・基礎スキル・安心感)
- 日系で経験を積んでから外資に挑む「ステップアップ戦略」
- 外資で内定を取る準備10ステップと、入社後2年間の成功ロードマップ
- 最終判断に役立つ「外資か日系かを選ぶ基準」
この記事を読めば、「外資か日系か」で迷っているあなたが、自分に合ったキャリアのスタート地点を選べるようになります。
なお、本記事における外資系企業は「海外の親会社が経営を管理し、社風も海外本社のカラーが色濃く反映されているところ」を前提にしていますのであらかじめご了承ください。
それでは外資系への就職について順番に解説していきます!

新卒で外資はやめとけ? まず結論と「向き・不向き」をチェック

外資系は「高収入・グローバルな経験」が魅力的です。
一方で「成果主義」「即戦力前提」「英語での業務環境」といった厳しい条件がそろうため、新卒にとってはハードルが高いのも事実です。
まずは、なぜ「やめとけ」と言われるのか、日系との違い、向き不向き、典型的なつまずきパターン、判断フロー、そして例外的に外資が向いているケースまでを整理します。
- 「新卒で外資系はやめとけ」と言われる背景外資と日系の違い
- 向いている人/向いていない人の特徴
- つまずきやすい典型パターン
- 判断フロー(キャリア→スキル→出口)
- 例外的に外資がハマるケース
なぜ「新卒で外資系はやめとけ」と言われるのか
外資系は、「研修を通じて成長したい」「会社には充実した教育制度を求めたい」人には厳しい環境です。
外資系企業が「新卒ではやめとけ」と言われる理由は大きく4つあります。
①解雇リスク
外資は成果主義で「結果を出せない人は雇用契約終了」という文化が強く、日本的な終身雇用や年功序列による人事はほぼありません。
実際、日系・外資系の両方を経験した私の経験では、外資系に勤務する社員の方が勤続年数が短い傾向にありました。
②研修制度の充実度
日系大手が「新卒一括採用+研修で育成」というスタイルをとるのに対し、外資は即戦力を前提にします。
外資系企業でも、専門性を高めるための研修はサポートしてもらえることもあります。
ただし、自分のキャリアは自分でデザインすることが前提です。
③英語力が求められる
業務の大半が英語で行われる部門もあります。
このような部門では、メール・会議・資料作成をすべて英語でこなす必要があり、英語が苦手だと大きなストレスになります。
また、英語を必要としない部門に配属されたとしても、昇進するためには海外本社や他のエリアの支社とコミュニケーションを取る機会も増えるので、将来的には英語力を身に付けておく必要があります。
④成果主義のプレッシャー
「努力の過程」よりも「数字」で評価されるため、決まった期間で成果を出せないと評価(給与)にシビアに反映されます。
評価されるためには、自分の成果をアピールすることも求められます。
「まじめにやっていれば見てくれているだろう」が通用しないのが外資系のカルチャーです。
外資系と日系の違いを超シンプルに解説
外資と日系の違いを整理すると、次のようになります。
| 項目 | 外資系 | 日系企業 |
| 評価基準 | 成果中心(数字・実績) | 過程・努力も評価対象 |
| 意思決定スピード | 速い(フラット) | 遅い(合意形成重視) |
| 役割 | 明確・ジョブ型雇用 | 幅広い・ゼネラリスト育成 |
| 研修 | 最小限(即戦力前提) | 手厚い(新卒一括採用前提) |
例えば、外資系の企業では、職種と役割が明確に決まる一方、日系では「まずは営業部で基礎を学んでから」というジョブローテーションのパターンが多いです。
外資系に向いている人/向いていない人のチェック
新卒で外資系を選ぶなら「自分のキャリアに対して主体的に動けるか」が最重要です。
私は10回の転職を経験しましたが、外資系でうまくいっている人は「自分の成果を数値化して説明できる人」でした。
逆に「上司が教えてくれるはず」「コツコツと言われたことだけをやる」と待つタイプはキャリアが停滞している傾向がありました。
外資系でつまずきやすい3つの典型的なパターン
外資系では「数字で語ること」「自ら提案すること」「相談と報告を密に行うこと」が重視されます。
外資系で失敗しやすい典型的なパターンは次の3つ。
- 「過程重視」思考:「努力を見てほしい」と思っても、外資では成果が全て。 例えば、営業で「訪問回数」や「残業時間」を評価する日系に慣れた人が、外資で「売上数字」しか評価されないと苦労します。
- 受け身の姿勢:上司から「これをやって」と指示が出るのを待つスタイルは通用しません。 外資は「自分から提案」する人材を評価します。
- 相談不足:成果が出なくても「誰にも相談せず」抱え込むと、評価面談で一気にマイナス評価になります。 問題を抱えた時には「自ら社内のリソース(上司・同僚)を使って解決する力」が求められます。
「自ら社内のリソース(上司・同僚)を使って解決する力」が求められます。
外資系に入社するか迷ったときの判断フロー
新卒で外資を選ぶかは「次の転職で売れるスキル」が得られるかで決めるのが合理的です。
新卒で外資に行くべきか迷う人は、次の判断フローを参考にしてください。
- 長期キャリア観:既に自分の専門性を特定し、5年から10年後に「専門職で市場価値を高めたい」なら外資系寄り。
- 初期配属の内容:自分の強みが活かせる部門に所属してキャリアをスタートできるか。成果主義の外資系での経験は強みになりやすい。
- 身につくスキル:英語・交渉力・データ分析力など「市場価値の高いスキル」が得られるか。
- 出口戦略:外資系での経験を「今後の転職市場」でどう活かせるか。
新卒でも例外的に外資系がハマるケース
外資系は「超優秀な人材」にはハイリターンですが、それ以外の多くの人には「まず日系で基礎を積んでから外資に挑戦」という方が現実的。
外資系が「やめとけ」と言われがちな中で、例外的に合う人もいます。
- 外資コンサル:論理思考力・STAR面接の対策ができる人なら新卒から挑戦価値あり。20代でも年収1,000万円超も可能。
- 外資IT:エンジニアとしてのスキルがあり、即戦力でコードを書ける人には絶好の環境。
- 外資金融:英語力+ファイナンスのスキル(経理・会計)が揃っていれば、20代で高収入を狙える。
筆者の知人で外資系コンサルに入社した人は、30代で年収2,000万円に到達しました。
ただし、激務で燃え尽きる人も多く、向き不向きは極端です。
外資系のデメリット5つ+先回りの対策

外資系企業は「高収入・グローバル環境」というメリットが目立つ一方で、入社後に「思っていたのと違う」と感じて早期退職につながるケースもあります。
特に 雇用の不安定さ・教育制度・英語や文化の壁・成果主義・福利厚生などが代表的なデメリットとして挙げられます。
ただし、これらは事前準備や対策である程度カバーできます。
ここでは、典型的なデメリット5つと具体的な回避方法を解説します。
- 雇用が不安定
- 教育制度・研修
- 英語・異文化の壁
- 成果主義のプレッシャー
- 福利厚生の差・上司ガチャ
①雇用が不安定
外資系は「市場からの撤退」や「突然のレイオフ(人員削減)」が起こりやすい環境です。
例えば、米国の大手テック企業が世界で数千人規模のレイオフを実施し、日本支社でも影響を受けました。
これは成果主義・株主還元が徹底しており、利益が出なければすぐにコスト削減に動く文化が背景にあります。
ただし、個人ができる対策もあります。
- KPI(重要業績評価指標)を明確化:入社時や期初に「何を成果と見なすか」を上司と握る。
- 成果の可視化:自分の業績を数値でまとめ、定期的に共有する。
- 実績メモ運用:自分の成果をポートフォリオ化し、転職市場でも使える形にしておく。
私も過去に勤務先が買収されたことにより、レイオフの対象になりかけましたが、すぐに転職できたのは「自分の成果を数値化して残していたから」です。
②教育制度・研修
外資系は即戦力を求めるため、日系のような手厚い新卒研修は期待できません。
多くの場合、数日のオンボーディング(会社説明やツールの使い方)で終わり、すぐに実務を任されます。
新卒には、日系と比較すると厳しい環境ですが、自分で学ぶ仕組みを作れば乗り越えられます。
具体的対策
- 90日のスキルアップ計画:入社3か月間で「業務理解・専門スキル・英語表現」の学習テーマを決める。
- 社内メンター探索:部署内で信頼できる先輩を見つけ、定期的に相談。
- 社外学習ルーティン:業務に必要な知識をUdemyなどのオンライン授業で学習。
③英語・異文化の壁
外資でよく聞くのが「英語が壁だった」という声です。業務内容によっては、会議・資料作成・チャットすべて英語でこなす場面もあります。
特にグローバル会議では、米国や欧州のスピード感ある議論についていけないと苦労します。
対策としては「用途別KPI」で鍛えること
- 会議:週1回は必ず英語で発言する(ネイティブスピーカーのシャドーイングが有効)
- 資料:月1本は英語でスライドを作る
- チャット:英語でのショートメッセージを毎日送る
また、異文化の違いも大きいです。
たとえば日本では「空気を読む」ことが重要視されますが、外資系では「言わないことは存在しない」と見なされます。
発言しないと「意見がない」「貢献する意識が低い」と解釈されるため注意が必要です。
④結果主義のプレッシャーへの対策
外資は成果主義で、成果が出なければ短期間で評価が下がります。
その結果、若手の離職率も高くなる傾向があります。
私は日系・外資系の両方の勤務経験がありますが、外資系は成果を出さないと退場させられるプレッシャーが強い傾向を実感しました。
プレッシャーに対する対策
- Quick Win設計:最初の90日で小さな成果をあえて狙う。例:新規提案・改善案を1件通す。
- 週次レビュー:上司と進捗を毎週共有し、期待値のズレを防ぐ。
- 相談先の確保:社内だけでなく、キャリアカウンセラーやOB/OGにも相談できる体制を持つ。
筆者も外資系に転職時に「入社3カ月で(小さくても良いので)目に見える成果を出すこと」を意識していました。
具体的には、入社時のフレッシュな目線で提案した業務改善の施策が採用され、その時に実質的にチームの一員となれた実感がありました。
⑤福利厚生の差・上司ガチャ
外資は給与が高い分、福利厚生が日系より劣る場合があります。
住宅補助や退職金制度がない企業も珍しくありません。
また、上司によって職場環境が大きく左右される「上司ガチャ」問題もキャリアにおける影響が大きいです。
日系企業に新卒で入る5つのメリット

日系企業は「終身(長期)雇用」や「新卒一括採用」を前提にしているため、外資に比べてじっくり育てる文化があります。
新卒で入社すれば、体系的な研修やジョブローテーションを通じて土台を作り、失敗をしながら学ぶ余地も多いです。
ここでは 育成制度・業務プロセス・長期雇用の安心感・多部門連携・配属ガチャの意外な利点 という5つの観点から、日系のメリットを整理します。
- 体系的な育成・ジョブローテで土台を作れる
- 業務プロセスと品質基準を徹底的に学べる
- 長期雇用と福利厚生の安心感
- 多部門連携で広い視野が育つ
- 配属ガチャでも基礎スキルは残る
①体系的な育成・ジョブローテで土台を作れる(配属・研修・面倒見の良さ)
日系大手企業の大きな強みは「育成前提で採用する」ことです。
入社後に数週間〜数か月の研修があり、ビジネスマナー、業務の基礎、会社の歴史まで一から学べます。
その後は ジョブローテーション(複数部署を経験させる制度)で、営業・企画・管理など幅広い仕事を体験するケースも多いです。
例えば、私の友人は大手メーカーに新卒で入り、最初は営業、その後は人事部門、さらには子会社への出向を経験しました。
このように自分の適性や会社の事情によって様々な職種を経験していきます。
②業務プロセスと品質基準を徹底的に学べる
日系企業は「業務の進め方」を細かく学べる場でもあります。
代表的なのが ホウレンソウ(報告・連絡・相談) です。
日系では「過程の共有」も求められるため、報告の仕方やチーム内での合意形成を徹底的に叩き込まれます。
また、外資系が効率性を重視するいっぽう、日系は品質基準に対するこだわりも強く、製造業などでは「一つの不良品も出さない」という姿勢が徹底されています。
こうした経験は、後々外資に転職しても「日本人特有の強み」として評価されやすいです。
③長期雇用と福利厚生の安心感
外資系と比べて、日系は雇用が安定しており、福利厚生も手厚いのが特徴です。
住宅補助・家族手当・退職金制度などは、多くの企業が維持しています。
これにより、安心して長期的にキャリアを考えられる環境が整っています。
外資では「結果を出さないと即評価ダウン」となるのに対し、日系では、良くも悪くも「成功・失敗が評価に与えるインパクト」が外資系ほど強くありません。
これはこれからキャリアを築いていく新卒にとって大きな安心感です。
④多部門連携で広い視野が育つ
日系企業は縦割りと言われがちですが、実際には複数部署との連携が必須です。
例えば、営業が顧客ニーズを拾い、商品企画に伝え、製造と調整し、さらに法務、経理や広報と連携する―こうした調整力を若いうちから鍛えることができます。
外資に転職した後も「日本企業での調整経験」は大きな武器になります。
グローバル企業でも日本法人は日系企業とやり取りすることが多いため、合意形成や根回しのスキルが評価されるのです。
⑤配属ガチャの中でも基礎スキルは汎用的に残る(可搬化しやすいスキル群)
「配属ガチャ」という言葉があるように、希望しない部署に配属されるリスクもあります。
しかし、実際にはどの部署でも基礎的なスキル(顧客対応、資料作成、数字管理など)が身につきます。
これらは外資・ベンチャー・他業界でも応用できる「可搬性(ポータブルスキル)」の高い力です。
また、ジョブローテーションが、自分の思わぬ適正に気づくきっかけになることもあるかもしれません。
私も希望とは違う部署に配属されたことがありますが、そこで身につけた「和文・英文の契約書のレビュースキル」は、その後の外資企業でも役立ちました。
ステップアップ戦略:まず日系→数年後に外資系に転職する方法とメリット

これまで説明したとおり、人によっては「新卒でいきなり外資」はリスクが高いです。
日系企業で基礎を作ってから外資に転じることでキャリアを大きく伸ばす「ステップアップ戦略」が現実的です。
日系で得た実務経験・社内調整力・育成環境を足場にし、外資系で高収入・裁量・グローバル経験を得る流れは、多くの転職成功者が実践しています。
私自身もこのようなキャリアパスを選んだことに満足しています。
ここでは橋渡しになる実務、転じるタイミング、準備の仕方、若手転職時の注意点を解説します。
- 外資系への橋渡しになる実務
- いつ外資系に転じるべきかのサイン
- 外資系にキャリアチェンジするコツ
- 第二新卒・若手転職の注意点
外資への橋渡しになる実務
外資に転職するときにもっとも重視されるのは「職種の一貫性」と「成果の可視化」です。
新卒で日系に入った場合でも、次のような実務は外資への橋渡しになります。
- 職種の軸を固める:営業なら「顧客開拓〜受注」、マーケなら「KPI設計〜施策実行」など、専門性を明確にする。
- 担当範囲を広げる:部分的な作業だけでなく「企画〜実行」まで関わる経験を積む。
- 定量成果を積み上げる:売上、契約数、コスト削減額など数字で語れる実績を持つ。
いつ外資系に転じるべきかのサイン
外資系に挑戦するタイミングは人によって異なりますが、目安となる「サイン」があります。
- 応募するポジションのJD(Job Description:職務記述書)の一致率が高い:募集要項の7割以上を満たせるとチャンス。
- 面接通過率が上がる:書類が通りやすくなった時点で市場価値が認められている。
- 社外評価の手応え:転職エージェントやヘッドハンターから外資求人を紹介され始める。
例えば、私が外資系に転職したときも、日系での成果が求人票にかなり一致していることを感じて応募しました。
外資系にキャリアチェンジするコツ
外資系に転じるときは「自分の実績を伝えられる形」にすることが重要です。
- 実績ポートフォリオ:エクセルやパワポに「成果・数字・役割」をまとめておき、応募企業ごとにアピールするものを抽出する。
- 英語運用強化:TOEICやIELTSなどのスコアだけでなく、実際の業務で英語を使った経験を語れるようにする。
- 海外案件の露出:日系でも「海外拠点とのやり取り」や「外国人顧客対応」があると評価が高い。
私が初めて外資系に転職した際には、日系企業における外国企業との取引実績をアピールし、実際に取引先の外資系企業から内定をもらったことがあります。
第二新卒・若手転職の注意点
第二新卒(入社3年以内の転職)や若手転職は、スピード感が強みですがリスクも伴います。
注意すべき点
- 職能の可搬性:今の経験を外資系に持っていけるか。補助的な業務だけだと弱いが、数値管理やプロジェクト推進なら評価される。
- 条件面の見極め:給与だけでなく「雇用安定性・上司との相性」も確認する。
- 失敗ラインの設定:合わなければ「第二新卒カード」で早めに撤退する判断を持つ。
外資系はジョブ型採用が基本のため、一度採用された職種から変わることはほとんどありません。
専門性を高めることができるメリットがあるいっぽう、キャリアが停滞する可能性があるため、転職するタイミングを見極めることが重要です。
外資系から内定→活躍までのロードマップ

外資系で内定を取り、実際に成果を出すまでには「入社前の準備」と「入社後の行動計画」が欠かせません。
就活段階では インターン参加・英語力強化・業界研究・応募書類の工夫・面接対策 がポイント。
入社後は最初の90日で信頼を得て、1年目で専門性の柱を立て、2年目で成果を可視化するのが成功の鍵です。
- インターン参加は重要
- 英語は用途別KPIで鍛える
- 業界・企業研究で差別化
- JDに沿った実績をアピール
- 書類は数字と役割で見える化
- 面接対策は反復練習と振り返り
- 志望動機は3つの「なぜ」
- 企業研究のための情報収集
- 資格は補助的な要素
- メンター活用・第三者レビュー
- 入社後は90日→1年→2年のロードマップで成果を積む
①インターン参加は重要
外資系就活ではインターンが内定に直結するケースが多いです。
特に外資系コンサルや金融は、インターンで高評価を得た学生がそのまま本選考に進み、内定を得る流れが一般的です。
逆にインターンに参加していないと、本選考で不利になるケースも少なくありません。
ポイント
- コンサル:ケース面接の実践経験が得られる
- 金融:分析・数理スキルを試される
- IT:プロジェクト参画型のワークが多い
筆者が勤務していた外資系映画会社は学生に人気の高い企業であったため、採用はもとより、インターンシップに参加することさえ狭き門でした。
早めに情報収集し、可能な限り応募するようにしましょう。
②英語は用途別にKPIを設定して鍛える
外資では英語は避けて通れません。
ただし、TOEICなどのスコアだけでは不十分で、実務で使えるかが問われます。
そこで「用途別KPI」を設定して鍛えるのがおすすめです。
- 会議:必ず1回は英語で発言する
- 資料:月に1回は英語スライドを作る
- チャット:毎日英語でメッセージを送る
私自身、面接官として多くの応募者と面接してきましたが、「TOEIC900点」でも英語で自分のことを語ることができない人は数多くいました。
スコアをアップすることも否定はしませんが、実戦で発音やスピード感に慣れることが何より大事です。
③業界・企業研究
外資系といっても業界や企業によって求められるスキルは大きく違います。
| 業界 | 特徴 | 求められるスキル |
| コンサル | 論理思考・問題解決 | ケース面接対応、プレゼン力 |
| IT | スピード感・技術力 | プログラミング・データ分析 |
| 金融 | 精緻な数理・判断力 | ファイナンス知識・英語交渉 |
| 製薬 | 科学的知見・規制理解 | 論文リサーチ・英語資料作成 |
| メーカー | グローバル供給網 | プロジェクト管理・語学力 |
業界・企業研究で深掘りできれば、より説得力のある志望動機をアピールすることができ、他の応募者との差別化になります。
④職務記述書(JD)→ STAR法で再現性を示す
外資では応募者の経験がJD(Job Description:職務記述書)にどれだけ合致しているかが重要です。
面接では、自分の実績を「STAR法」で語ると説得力が増します。
- Situation(状況):どんな場面か
- Task(課題):自分の役割は何か
- Action(行動):具体的にどう動いたか
- Result(成果):数字や事実でどう変わったか
例えば「営業で前年比120%を達成」という実績を「新規顧客開拓プロジェクトの責任者として〜」とSTAR法で説明すると、面接官に伝わりやすいです。
⑤応募書類は数字・役割・工夫で書く(成果の見える化)
外資系では「履歴書や職務経歴書」が書類選考突破のカギです。ポイントは 数字・役割・工夫 の3点です。
実績の記載例:
- 「売上を伸ばした」 → 「新規開拓で前年比120%を達成(売上+5000万円)」
- 「チームで貢献」 → 「5人チームのリーダーとして〇〇の施策を企画・実行」
- 「改善を実施」 → 「〇〇の業務フローを改善し、〇〇の工数を20%削減」
英文のレジュメを作成する際に、日系と外資系の双方に応募する際に多く見られるのは、和文の経歴書をそのまま英訳するパターンです。
英文のレジュメは必ずゼロベースで外資系に刺さる書式・表現を使って作成するようにしましょう。
⑥面接・ケース・技術選考は「型→模擬→振り返り」で反復
外資系の面接は独特です。特にコンサルではケース面接、ITでは技術試験が一般的です。成功のカギは「型を覚える→模擬面接で実践→振り返り」の繰り返しです。
- 型:書籍やセミナーで基本フレームを習得
- 模擬:OB訪問やオンライン面接練習で実戦訓練
- 振り返り:録音・録画で自分の改善点を客観的に把握
また、志望度の高い企業の面接の前に、他の企業で実際の面接を経験しておくこともおすすめです。
⑦志望動機は「なぜ外資系/なぜその企業/なぜ自分なのか」の3点セットで差別化
外資では「志望動機」は必ず深掘りされます。効果的なのは 3点セット です。
- なぜ外資系:成果主義・グローバル経験を求めるから
- なぜその企業:業界ポジション・強み・企業文化に共感
- なぜ自分なのか:自分の実績・スキルがその社の課題に合致している
これらの要素を整理して、面接ではSTAR形式で自分の実績をアピールすれば選考の通過率も高まります!
⑧企業研究の情報源
外資就活の情報は日系より得にくいため、複数の情報源を組み合わせる必要があります。
- 公式HP:募集要項や事業戦略
- OB/OG:リアルな現場の声
- コミュニティ:SNSや就活サークルでの情報交換
- 外資就活サイト:最新の選考情報・ES通過例
- 口コミサイト:社員のリアルな声
⑨資格・スコアは「補助的な要素」
外資では資格やスコアは「必須条件」ではなく「補助的な要素」に過ぎません。
TOEIC900点よりも「英語でプロジェクトをリードした経験」が重視されます。
アピールの実例:
- TOEIC900点+「〇〇のプロジェクトの責任者を務め、プロジェクトをリードした」
- 簿記2級+「財務諸表を用いた改善提案」
⑩メンター活用・就活のプロに頼る
外資就活は一人で進めるには難易度が高いです。そこで効果的なのが メンターや就活のプロ の活用です。
- OB/OG:面接での本音や選考の裏事情を知れる
- 新卒向けの人材紹介サービス:書類添削や面接練習のサポート
- メンター:客観的に強みと弱みを指摘してくれる
私も外資系に転職した際には、転職エージェントの添削を受けて、書類選考の通過率を大幅に改善できました。
90日プラン:役割の確認・KPI設定・Quick Winで信用を作る
入社後の最初の90日は「試用期間」とも言える重要なフェーズです。
このフェーズでは、自分の存在を認識してもらうことが大切になります。
- 上司と役割とKPIを握る
- 小さな成果(Quick Win)を作り、信頼を得る
- 所属部門のメンバーとの関係を築く
1年プラン:上司・横連携・海外拠点との関係構築/専門性の柱を立てる
1年目は「人脈」と「専門性」を固める期間です。
- 上司・同僚との信頼関係の構築
- 海外拠点とのやり取りを経験
- 専門性の柱を立てる(例:マーケティング分析のエキスパート)
2年プラン:成果の整理・評価面談対策・外資系からの撤退基準の明文化
2年目は「成果を形に残す」ことが重要です。
- 実績をドキュメント化(売上、改善、プロジェクト成果)
- 評価面談に備えて自分の実績をデータを使って整理
外資系が合わない場合の撤退基準(第二新卒枠を活用して日系に転職)を決めておく
まとめ:外資系と日系、どちらから始めるか最終判断の基準

就職や転職で「外資から行くか、日系から行くか」を決めるのは、多くの人にとって大きな悩みです。
日系と外資系には様々な違いがあり、どちらが正解かは「自分のキャリア観」によって変わります。
ここでは最終判断のための基準を整理しました。
筆者自身も10回の転職の中で、日系→外資→日系→外資と行き来しました。
その経験からも「日系でじっくり学び、外資で早いサイクルで成果を出す」が現実的で、多くの人に適したパターンだと考えます。
✅ 結論:
- 挑戦意欲と実力が揃っているなら外資スタートもアリ。
- 迷うなら日系で基礎を積み、数年後に外資で飛躍するステップアップ戦略がベスト。
大切なのは「どちらに行くか」よりも「どんなスキルを積み、次のキャリアにどう活かすか」です。
外資か日系か、正解は一つではありません。外資は挑戦の場、日系は基礎を磨ける場。
大事なのは「どこに行くか」よりも「そこで何を学び、次にどう活かすか」です。
私自身、10回の転職で日系と外資を行き来しましたが、後悔した選択はありません。
この記事が外資系への就職を検討している人にとって少しでも参考になれば幸いです。
最後まで読んで下さりありがとうございました!