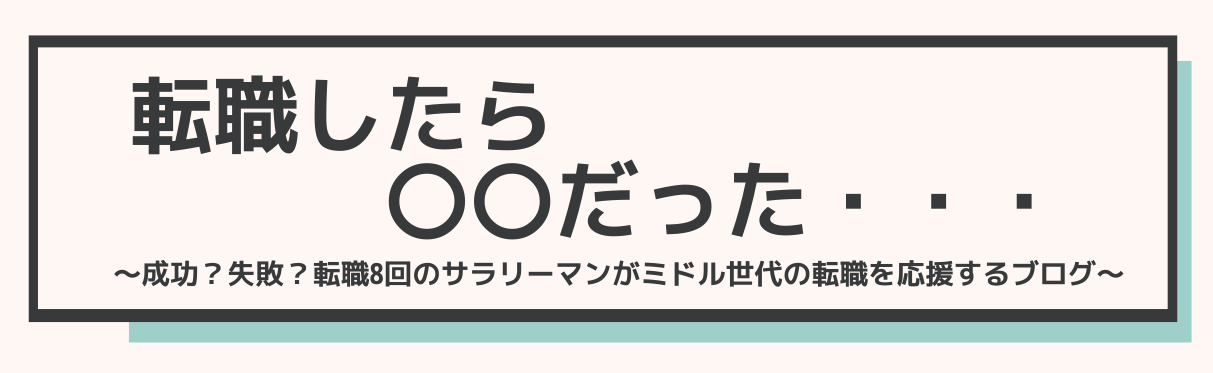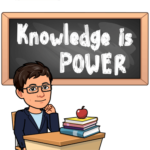静かな退職とは?メリット・デメリットと対処法を解説!

「最近、仕事にやる気が出ない…でも辞めたいわけじゃない」─ そんなふうに感じていませんか?
もしかするとそれは、今話題の「静かな退職」かもしれません。
私自身、11社での勤務を経験してきた中で、実は静かな退職の状態にハマったことがあります。
「静かな退職」とは、「会社を辞めずに、必要最低限だけ働く」という選択。
エン・ジャパン社が実施した「静かな退職 実態調査」による概要は次のとおりです。
- 5社に1社が「静かな退職」状態の社員がいると回答
- 300名以上の企業は90%が「いる」または「いる可能性がある」と回答
- 「静かな退職」状態の社員の役職は「一般社員」が多い
- 「静かな退職」状態の社員の職種は「バックオフィス」が多い
この記事では、
なぜ静かな退職に陥るのか?
どんな兆候があるのか?
そして抜け出すために何ができるのか?
を、実体験とデータを交えてわかりやすく解説しています。
たとえば、
- 今の職場で働き続けても成長できる気がしない
- 周りにやる気がある人が少なく、自分だけ浮いてる気がする
- 昇進や評価に興味がなくなってきた
そんなモヤモヤを抱えている方にこそ、読んでほしい内容です。
この記事を読み終えたときには、「自分にとってベストな働き方って何だろう?」という疑問に対するヒントがきっと見えてきます!
静かな退職を正しく理解して、「うまく付き合いながら自分らしく働く方法」を一緒に探してみませんか?
- 静かな退職とは「必要以上に働かない」働き方
- サイレント退職との違いや背景にある社会変化
- 静かな退職に陥りやすい5つの原因
- 兆候をセルフチェックできる具体的なサイン
- メリットとデメリットの両面を客観的に整理
- キャリアの棚卸し・外部相談・リスキリングなど具体的な対処法を提案
- 「静かな退職状態から抜け出す6つの方法」で行動に移せる内容も網羅

静かな退職とは?言葉の意味と誤解を整理しよう

「静かな退職(Quiet Quitting)」という言葉を見聞きした人も多いのではないでしょうか。
これは突然辞めることではなく、「会社に必要以上の労力や感情を注がない働き方」を意味します。
近年では海外のZ世代を中心に広まり、日本でも注目されています。
ただし、「サイレント退職」とは意味が異なるので注意が必要です。
ここでは静かな退職を以下のポイントから説明していきます。
- 静かな退職とは「必要以上に働かない」状態
- サイレント退職とは違う?よくある誤解
- ハッスルカルチャーからの価値観の変化
- 海外発のトレンドが日本でも注目される理由
静かな退職とは「必要以上に働かない」状態
静かな退職(Quiet Quitting)とは、「必要な範囲で仕事はこなすが、それ以上はやらない」という働き方のことです。
残業や休日対応、責任外のタスク等には関わらず、与えられた業務を淡々とこなすスタイルを指します。
例えば、ある営業職の人が
「最低限のノルマは達成するけど、ノルマ以上の業務や担当業務に直結しない資料作成や他の社員のサポートはしない」
といった状態が静かな退職にあたります。
この言葉が話題になったのは2022年に、キャリアコーチのBryan Creely(ブライアン・クリーリー)氏がTikTokで「Quiet Quitting」に関する動画を投稿し、バズったのがきっかけです。
静かな退職のポイント:
- 仕事は辞めないが、仕事に対する高いモチベーションはない状態
- 「頑張っても報われない」経験からやる気が減退しているケースが多い
- 決して怠惰ではなく「過剰な自己犠牲をやめる」選択ともいえる
サイレント退職とは違う?よくある誤解
静かな退職と混同されがちなのが「サイレント退職(Silent Resignation)」です。
これは、何の前触れもなく退職することを指し、会社側からすると“突然の離脱”になります。
一方の静かな退職は、「退職するわけではない」ことが特徴です。
仕事を最低限にとどめつつ、現職にはとどまるという選択です。
| 比較項目 | 静かな退職 | サイレント退職 |
| 退職の有無 | 辞めない | 辞める |
| 業務態度 | 必要最低限の業務のみ | 辞める前兆なし |
| 会社からの視点 | 徐々にやる気が見えなくなる | ある日突然いなくなる |
この違いを理解していないと、「やる気のない社員が辞めた=静かな退職」と誤解してしまうため注意が必要です。
ハッスルカルチャーからの価値観の変化
「ハッスルカルチャー(Hustle Culture)」とは、成功のためにはプライベートを犠牲にし、寝る間も惜しんで働くべきだ、という価値観を指します。
いわゆる“社畜”や“24時間働けますか”のような昭和・平成の労働観に近いものです。
しかし、コロナ禍や働き方改革の流れの中で、この考え方に疑問を持つ若者が増えています。
たとえば、以前は「遅くまで残業している人=頑張っている人」と評価された文化が、現在では「タイムマネジメントができない」と捉えられることもあります。
ワーク・ライフバランス社の調査によると、長時間労働に対する志向は「この先、より長い時間働きたくない」の回答が3割超で最多となっています。
(出典:企業の働き方改革に関する実態調査)
つまり、静かな退職は「やる気がない」のではなく、「自分の人生を守るための選択」として生まれてきたともいえるのです。
海外発のトレンドが日本でも注目される理由
静かな退職は、アメリカや中国の若者の間で広がった後、日本でも関心を集めました。
背景にあるのは、グローバル化したSNSと、働き方改革の潮流です。
特にTikTokやInstagramで海外の「Quiet Quitting」に関する投稿が拡散され、日本のビジネスパーソンにも共感を呼びました。
もともと日本では勤務先に対するエンゲージメントが低い傾向があります。
さらに、日本でもテレワークの普及や副業解禁、ジョブ型雇用の導入が進んだことで、「会社に依存しすぎない働き方」を選ぶ人が増えたのです。
たとえば、あるIT企業で働く30代男性は「スキルを活かせばどこでも働けると思い、会社に過剰な忠誠を持つのをやめた」と話していました。
こうした背景が重なり、日本でも「静かな退職」が“新しい働き方のひとつ”として受け入れられつつあります。
なぜ静かな退職を選ぶ人が増えているのか

静かな退職を選ぶ人が増えている背景には、働き手の価値観や会社への期待が大きく変わってきていることがあります。
特に、
「頑張っても報われない」
「働きすぎて私生活を犠牲にしている」
と感じる若手層を中心に、自分を守る手段としてこの働き方が浸透しています。
ここでは静かな退職を選ぶ人が増えている背景についてみていきましょう。
- ワークライフバランスを重視する人の増加
- 評価制度やキャリアパスへの不信感
- エンゲージメント(職場への愛着心)の低下
- 若手社員に多いリアリティショックとは?
- 熱意だけでは報われない時代の価値観シフト
ワークライフバランスを重視する人の増加
かつては「仕事優先」が当たり前だった日本社会ですが、近年は仕事と私生活のバランスを重視する人が明らかに増えています。
特に20〜30代の若手世代は「ほどほどに働き、自分の時間も大切にしたい」と考える傾向が強くなっています。
たとえば、内閣府の国民生活に関する世論調査(令和6年)によると、回答者の約4割が「収入よりも自由時間をもっと増やしたい」と答えています。
(出典:https://survey.gov-online.go.jp/living/202412/r06/r06-life/#sub26)
これは、長時間労働によって体調や人間関係を壊した経験のある親世代や先輩社員を見てきた影響も大きいでしょう。
コロナ禍で在宅勤務が普及したことも、時間の使い方を見直すきっかけになりました。
結果として、「必要以上に頑張らない働き方=静かな退職」が、自己防衛の手段のひとつに選ばれているのです。
評価制度やキャリアパスへの不信感
「一生懸命働いても評価されない」「上司の好き嫌いで昇進が決まる」と感じた経験はありませんか?
多くのビジネスパーソンが、評価制度やキャリアパスの不透明さに不満を持っています。
たとえば、担当の業務範囲外でも積極的に手を上げて働いてきた同僚が、まったく報われないのを見て「頑張る意味がない」と静かな退職を選ぶケースもあります。
このような貢献が評価される仕組みが見えにくい環境では、社員は「感情を切り離す」ことで自分を守ろうとします。それが静かな退職の根底にある感情です。
エンゲージメント(職場への愛着心)の低下
エンゲージメントとは「会社や仕事への愛着・信頼・やる気」のことです。
これが低下していることが、静かな退職の大きな原因のひとつです。
2024年のGallup社の調査によると、日本の社員のエンゲージメントは6%しかないという結果が出ています。
主要国での平均が23%となっていますので、日本はかなり低いことがわかります。
エンゲージメントが低いと、仕事に対して「やらされ感」が強くなり、やがて「必要最低限でいいや」となります。
たとえば、部内で誰が頑張っても評価が変わらない状況では、「どうせ頑張ってもムダ」と感じるのが人間の自然な心理です。
つまり、静かな退職は「サボりたいから」ではなく、「頑張りに対して報いてくれない勤務先に対して心が離れている」ことの表れと言えるでしょう。
若手社員に多いリアリティショックとは?
「リアリティショック」とは、入社前に思い描いていた理想と、実際の職場とのギャップにショックを受ける状態のことを指します。
たとえば、内定時に「風通しがよい職場」と聞いていたのに、実際は上司が一方的で部下の意見が通らないなどのケースがこれに当たります。
新卒社員の3年以内離職率は30%を超えていることは周知のとおり。
リアリティショックを受けた若手人材は、「転職する」か「とりあえず辞めずに働くけど、無理はしない」という選択に至ることが多く、後者の場合はそれが静かな退職という形で現れます。
熱意だけでは報われない時代の価値観シフト
「がむしゃらに頑張ればいつか報われる」
– こうした価値観は、かつての高度経済成長期においては終身雇用制度とともに機能してきました。
しかし現代では、成果主義・非正規雇用・副業解禁などによって、頑張りが必ずしも報酬につながらない時代になりました。
たとえば、「退職者の業務もカバーしたのに昇給は3000円だけ」という現実に直面すれば、「そこまでやる必要ある?」と感じるのは自然です。
実際、Job総研の調査でも「社員の75.2%が会社からの評価に不満と感じている」と報告されています。
(出典:https://jobsoken.jp/info/20230919/)
こうした価値観の変化が、“静かな退職”という現象を後押ししているのです。
静かな退職のサインとセルフチェック項目

「静かな退職」は自分でも気づかないうちに始まっていることがあります。
ここでは自分が静かな退職の状態にあるかチェックするための項目を紹介します。
以下の4つの項目に当てはまるかどうか、自分の働き方を一度チェックしてみましょう。
- 仕事への意欲や関心が薄れていないか?
- 必要最低限の仕事しかしていない
- 成長したいという気持ちがなくなっている
- 昇進や評価に対して無関心になっている
仕事への意欲や関心が薄れていないか?
「今の仕事にワクワクしているか?」
「最近、自分から積極的に動いたことがあるか?」
そう聞かれて、パッと答えられないなら、要注意かもしれません。
たとえば、以前は会議で積極的に発言していた人が、「言っても変わらないし、まあいいや」と思って意見を言わなくなる。
「新しいプロジェクトに関わってみたい」という気持ちがなくなる。
このような変化は、意欲の低下のサインです。
これは「燃え尽き症候群(バーンアウト)」の一歩手前の状態と言えるかもしれません。
意欲がなくなると、静かな退職に自然とシフトしていくことが多いのです。
必要最低限の仕事しかしていない
「言われたことはやるけど、それ以上はしない」。
それ自体が悪いわけではありません。
ただ、以前は「もっと良いやり方を提案してみよう」と思っていた人が、今は指示待ちになっているなら、それは静かな退職の兆候かもしれません。
たとえば、チームで業務改善を提案する文化がある職場で、
「時間がもったいないし、どうせ通らないからやらない」
と感じるようになった場合、それは意識的に「積極的な関与を減らしている」状態です。
このような姿勢は「ディスエンゲージメント(職務から心理的に距離をとる状態)」と呼ばれ、現在の仕事に対する高い意欲が失われている可能性があります。
成長したいという気持ちがなくなっている
「もっと学びたい」「スキルを伸ばしたい」と思えていた頃に比べて、今はどうでしょうか?
もし「現状維持で十分」「学んでも報われない」と感じるようになっていたら、それは静かな退職の初期段階かもしれません。
たとえば、以前は外部セミナーに積極的に参加していた人が、「参加しても評価や昇給に直結しないから」とスルーしてしまう。
上司に研修の話を振られても「それって何のメリットがあるんですか?」とやらない理由を探してしまう。
このような変化は、成長意欲の減退を示しています。
「学習意欲の低下」はキャリア停滞の前兆であり、自己肯定感やモチベーションの低下にも直結するとされています。
こうした内面的な変化は、自分ではなかなか気づきにくいからこそ、意識してチェックすることが大切です。
わたしの場合は、「成長のためにプライベートの時間を割けるか」がひとつのバロメーターになっています。
昇進や評価に対して無関心になっている
「昇進したいと思わない」「評価されてもどうせ給料は変わらない」と感じるようになったら、それも静かな退職の大きなサインです。
たとえば、かつては半期ごとの人事面談に向けてアピール材料を準備していたのに、今は「話しても意味ない」と何も用意しない。
そんな変化は、「がんばりの回収」に期待しなくなった証拠です。
転職サービスを提供するアデコ社の調査によると、ビジネスパーソンの6割以上が「社内評価制度に納得していない」と回答しています。
このような状態が継続すると、昇進や評価に無関心になり、周囲の期待にも応えようとしなくなり、それが結果的に「静かに働く」姿勢へとつながっていくのです。
静かな退職で得られるメリットとデメリット

静かな退職は「仕事をほどほどにする」スタイルだからこそ、ストレスが減ってプライベートに割ける時間が多くなる効果があります。
一方で、自分の将来や人間関係に思わぬ影響を及ぼすことも。
自分にとってのメリット・デメリットを知っておくことが、後悔のない選択につながります。
ここでは、静かな退職で得られるメリットと失うものについて、私の経験をもとに説明していきます。
- メリット①:ストレス軽減と私生活の充実
- メリット②:仕事に縛られない自由な時間
- デメリット①:成長機会や評価の停滞
- デメリット②:周囲との関係悪化の可能性
- デメリット③:キャリアに影響することも
メリット①:ストレス軽減と私生活の充実
静かな退職の大きなメリットは、精神的な負荷が軽くなり、生活にゆとりが戻ることです。
たとえば、「納期に追われるプレッシャー」や「人間関係の摩擦」に無理して関わらなくなったことで、心がすっと軽くなったという声は少なくありません。
仕事に自分のエネルギーを100%注がなくなると、
「家族との会話が増えた」
「趣味に打ち込めるようになった」
といった変化も生まれます。
実際に、わたしの場合は、ある勤務先で静かな退職状態にあったとき、フルフレックスの職場だったこともあり朝7時に出勤して16時に退勤する生活を送っていたことがあります。
その時は仕事での充実感は感じられませんでしたが、プライベートはとても充実し、健康的な生活を過ごしていました。
「健康第一」と思ったとき、静かな退職は「自分を守る働き方」として価値がある選択です。
メリット②:仕事に縛られない自由な時間
静かな退職を選ぶことで「仕事だけの人生」から脱却し、自分の時間を確保できるようになります。
これは副業や趣味、資格取得といった「第2の軸」を持つ人にとって大きなメリット。
たとえば、フルタイムで働きながらも、定時に退勤して動画編集を学んだり、英会話レッスンを受けたりしている人は、無理に会社に合わせるのではなく、自分のペースを優先しています。
株式会社イトーキの調査によると、「従業員の自己裁量が高いほど、生産性とパフォーマンスが高くなる」というデータが紹介されています。
(出典:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000037.000032317.html)。
つまり、静かな退職は「自分の時間とエネルギーの配分を自分でコントロールする」ための第一歩ともいえるのです。
デメリット①:成長機会や評価の停滞
一方で静かな退職を選ぶと、目の前のプレッシャーは減っても、長期的なキャリアの成長機会を逃すことにもつながります。
たとえば、上司から新しい業務を打診されても断ってしまうと、結果として「成長のチャンス」や「異動・昇進の話」からも外れてしまいます。
人事評価制度では「成果」だけでなく「積極性」や「チャレンジ意欲」も評価されることが多くなります。
従って、静かに仕事をこなしているだけでは「伸びしろがない」「会社に貢献する意欲が低い」と判断されやすいのです。
パーソル総合研究所の調査によれば、
「成長実感がある社員は、仕事へのモチベーションが3倍高い」
と報告されており、成長機会が減ることは“意欲低下”のループにもつながる恐れがあります。
(出典:https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/column/201711011100.html)
デメリット②:周囲との関係悪化の可能性
静かな退職を選ぶことで、「自分の仕事だけこなせばOK」という姿勢が強まると、職場での人間関係に影響することもあります。
たとえば、チームで助け合う文化の職場で、自分だけが「それは自分の担当外です」と言い続けると、同僚から「冷たい人」「協調性がない」と見られやすくなります。
このような心理的距離感が継続すると、信頼関係が築けず、情報共有やサポートも得にくくなり、「孤立感」を感じるようになるケースもあります。
また、自分が周りのサポートを必要とするときに気まずくなってしまうことも。
つまり、人間関係を築く余力がない働き方は、長期的に見てリスクにもなり得るのです。
デメリット③:キャリアに影響することも
静かな退職の状態が長く続くと、「意欲がない人」「変化に適応できない人」という印象を持たれ、次のキャリアの場でもマイナスになる可能性があります。
たとえば、転職の面接で「今の職場で何を得ましたか?」と聞かれたときに、成長体験を示す具体的な回答ができないと、採用担当者は「新しい環境でも淡々とこなすだけかも」と受け取ることがあります。
つまり、静かな退職状態は短期的には“楽”に見えても、転職市場では“リスク”として捉えられることもあるのです。
今の会社を離れる予定がない人でも自分の意思とは関係なく転職活動を余儀なくされることもあります。
大手電機メーカーや自動車メーカーが数万人規模のリストラを行うことからも、いま企業は限られたリソースで最大限の成果を出すことが求められています。
企業は、静かな退職を求める人材よりも積極的に貢献する意欲のある人材を選ぶ傾向にあることを意識しておきましょう。
静かな退職から抜け出す・乗り越える方法

静かな退職状態に気づいたら、まず焦らずに「立ち止まること」が大事です。
今すぐ大きく変わる必要はありません。
でも、自分のキャリア・生活の軸を見直したり、小さな行動を積み重ねたりすることで、少しずつ前に進むことはできます。
あなたの突破口になるかもしれない6つの方法を紹介します!
- キャリアの棚卸しで「自分の軸」を見直す
- セルフキャリアドックや外部相談の活用
- リスキリングで再び仕事に意欲を持つ
- 社内異動や転職で環境を変えてみる
- メンターや信頼できる人に本音を話す
- 筆者のおススメ:最低限の成果は出してプライベートも充実させる
①キャリアの棚卸しで「自分の軸」を見直す
「なんかやる気が出ない…」と感じたら、まず自分の過去のキャリア・経歴を振り返るのがオススメです。
これを「キャリアの棚卸し」といいます。やり方はシンプルで、以下のように書き出してみましょう。
- これまでやってきた仕事内容
- やっていて楽しかったこと
- 周囲から褒められた経験
- 自分が大切にしたい価値観(例:安定性・挑戦・成長)
- 二度とやりたくない仕事
たとえば「営業時代に後輩を育てるのが好きだった」と気づけば、「教育」や「サポート」を軸にした働き方に転じるヒントになります。
「やりがい」や「モヤモヤ」の正体は、自分の経験を棚卸し、気持ちを整理することで見えてきます。
②キャリアコンサルティングやキャリアコーチの活用
「ひとりで考えても答えが出ない…」と感じたら、第三者のサポートを借りてみるのも効果的です。
おすすめなのが転職エージェントの「キャリアコンサルティング」やキャリアコーチの利用です。
転職エージェントに登録すると、担当のキャリアコンサルタントとの面談が設定されます。
経験豊富なキャリアコンサルタントと自分のキャリアを言語化することで、これまでの経歴を整理し、今後のキャリアプランのアドバイスを受けることができます。
また、有料になりますが、ポジウィルキャリアのようなマンツーマンによるキャリアコーチングを利用することで、長期的な視点でキャリアアドバイスを提供してもらえます。
公的機関を利用することもできます。
厚労省の「キャリア形成・リスキリング支援事業事業」では、キャリア形成やリスキリングの相談や支援が無料で受けることができます。
人に話すことで自分の考えが整理されることは多いはず。
特に利害関係のない相手だと、「本音」が出しやすくなるので、思わぬ気づきを得られることもあります。
③リスキリングで再び仕事に意欲を持つ
「今の仕事がつまらない」と感じる背景には、「できることが限られている」という閉塞感があるかもしれません。
そんなときは、「リスキリング(学び直し)」を通じて、新しいスキルや可能性を広げてみるのがおすすめです。
たとえば、営業職の人がマーケティングやデータ分析のスキルを身につけると、仕事の視野も広がり、異動や転職の幅もぐっと広がります。
私の場合は、
ELSA Speak:英会話アプリで英語力の維持・改善。英語はどの企業・業界でも活用できる強力なポータブルスキルです。
Udemy:オンライン講座でマーケティング、プレゼン資料の作成方法、デザイン理論などを学んでいます。気になる講座をチェックしておいて、セール時にまとめて購入するのがおススメです。
④社内異動や転職で環境を変えてみる
同じ職場、同じチームに長くいると、どうしても「今さら変えられない空気」に包まれがちになります。
そんなときは、思い切って環境を変えることも視野に入れてみましょう。
たとえば、同じ会社でも部署が変わるだけで、人間関係や評価の方法がまったく違うということもあります。
また、転職によって「自分らしく働ける場所」が見つかるケースも少なくありません。
パーソルビジネスプロセスデザイン社の「転職と健康経営に関する調査結果」によると、転職経験者は「仕事満足度」が転職後に27%(13%から40%)上昇したと回答しています。
大事なのは、「今の場所がすべてではない」と知ること。選択肢があるとわかるだけでも、気持ちが前向きになります。
⑤メンターや信頼できる人に本音を話す
モヤモヤしているときに、自分の中だけで悩みを抱えてしまうのはつらいですよね。
そんなときは、信頼できる上司や先輩、あるいは職場外の友人や元同僚に、ざっくばらんに本音を話してみることがとても有効です。
たとえば「最近、仕事に対する意欲が低下しているように感じる」と話すだけでも、「それってこういう理由じゃない?」と意外な気づきをくれることがあります。
「メンター」とは、仕事やキャリアにおける指導者・相談相手のこと。職場内外問わず、話せる相手がいるだけで安心感がまるで違います。
⑥筆者のおススメ:最低限の成果は出してプライベートも充実させる
「もう、時間もエネルギーも仕事に振り切るのはしんどい…でも、まったくやる気がないわけじゃない」
─ 静かな退職の状態において、私がこれまで10回の転職経験から一番おススメしたいのが、「頑張りすぎない成果主義」という働き方です。
これは、私がプライベートを犠牲にして仕事にコミットした経験と静かな退職状態になった経験を経てたどり着いた働き方です。
これは、会社にすべてを捧げるのではなく、「自分の得意領域で効率的に成果を出しつつ、空いた時間をプライベートに充てる」というバランス型のスタンスです。
たとえば、「自分の専門性を発揮できる」と感じる分野に集中して、他のことには過剰に手を出さない。
それによって、評価を一定以上保ちながら、平日の夜や週末の時間を使って趣味・副業・家族との時間に注力する。
ー これが現代の「賢い働き方」になりつつあります。
私の場合は、勤務先では中の上から上の下あたりの評価を狙うくらいのリソースを投下して、それ以外の時間は家族との時間、副業、投資、ジム通いなどに割り振る、くらいのバランスが心地よい働き方になっています。
つまり、「成果=時間や精神を削るもの」ではなく、“自分のスキル・経験を活かす”ことで無理なく出せるものだと捉え直すことが大切です。
「頑張らない=無価値」ではなく、「プライベートを犠牲にすることなく成果を出す」ライフスタイルを目指すこと。
無理せず、でも手を抜かず、そんなちょうどいい働き方も選択肢のひとつになります。
静かな退職とは? この記事のまとめ
「静かな退職」という言葉、最初はちょっと他人事や海外のトレンドのように感じるかもしれません。
でも、実は心のどこかで「もう頑張りすぎたくない」と思っている人にとって、かなりリアルなテーマなんです。
この記事では、静かな退職の意味や背景、陥りやすいサインから、そこから抜け出すための具体的なステップまでをご紹介してきました。
働き方が多様化するなかで、「何が正解か」は人それぞれ。
でも、自分の気持ちにフタをしたまま何となく働き続けると、気づいたら大事なものを見失っていた…なんてことにもなりかねません。
だからこそ、「このままでいいのかな?」と感じたときに立ち止まって、自分と向き合う時間を持つことが大切です。
静かな退職は、悪いことではありません。だけど、そこにとどまる必要もありません。
あなたには、自分らしく働ける環境を選ぶ力があります。
もし今の職場でその答えが見つからないなら、新しい一歩を踏み出すことも選択肢のひとつです。
それでは、この記事のおさらいです!
- 静かな退職とは「辞めずに、最低限だけ働く」働き方
- 背景にはエンゲージメント低下・価値観の変化・評価制度への不信などがある
- 自分が静かな退職状態にあるかどうかは、意欲・関心・行動パターンでチェックできる
- 一時的にはストレス軽減のメリットがあるが、成長機会や人間関係、キャリアに影響することも
- 抜け出すには、キャリアの棚卸し、リスキリング、外部相談、環境を変えるなどの手段がある
- 大切なのは、「自分に合った働き方・生き方」を見つけること
この記事が今後のキャリアに悩む方にとって少しでも参考になれば幸いです。
最後まで読んで下さりありがとうございました!